「AIが仕事を奪う」「AIに負けてしまう」そんな不安を抱いている人も多いかもしれません。しかし、AI時代は決して恐れるものではありません。むしろ、新しい可能性に満ちた楽しい時代なのです。今回は、中学生でもわかりやすく、生成AIとAIの違いから始めて、AI時代を楽しく歩む方法をご紹介します。
まずは基本から!「AI」と「生成AI」って何が違うの?
テレビやニュースでよく聞く「AI」と「生成AI」。実は、この2つには大きな違いがあります。料理に例えると、とてもわかりやすくなります。
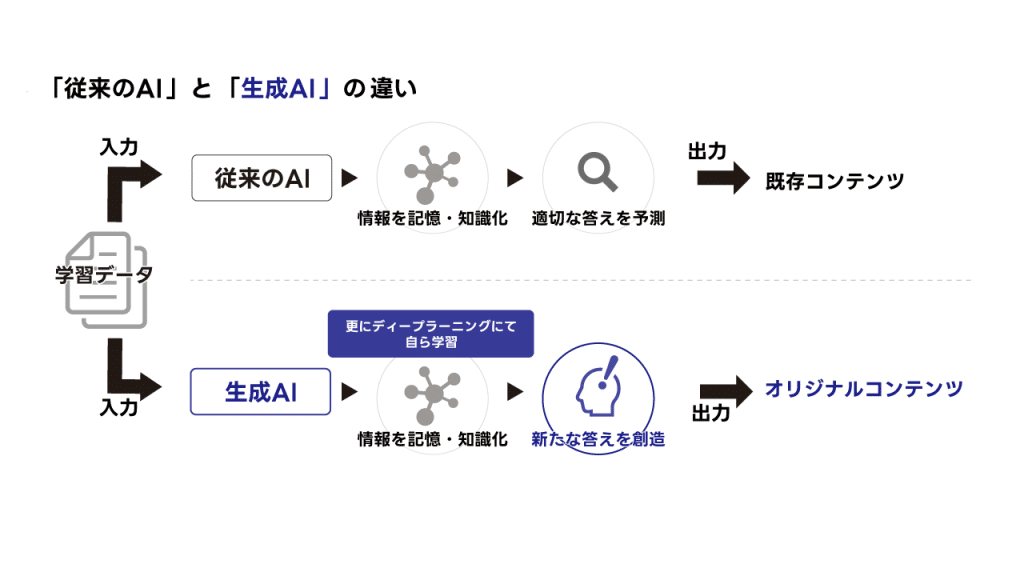
従来のAI:「レシピ本から料理を選ぶシェフ」
従来のAIは、あらかじめ決められたレシピ(データ)の中から、最適な料理(回答)を選んで提供してくれます。例えば:
- 天気予報の予測
- スマートフォンの音声認識
- 商品のレコメンド機能
- 自動運転の判断システム
生成AI:「オリジナルレシピを考え出すシェフ」
生成AIは、今までにない新しい料理(コンテンツ)を1から作り出すことができます。例えば:
- ChatGPTによる文章作成
- 画像生成AI(DALL-E、Midjourney)
- 音楽生成AI
- 動画生成AI

8年前と今、何が変わったの?総務省の調査で見る意識の変化
平成28年(2016年)、総務省が発表した調査結果は、現在のAI時代を予測する上で非常に興味深い内容でした。当時と現在を比較してみましょう。
平成28年当時:AI時代に必要とされた能力
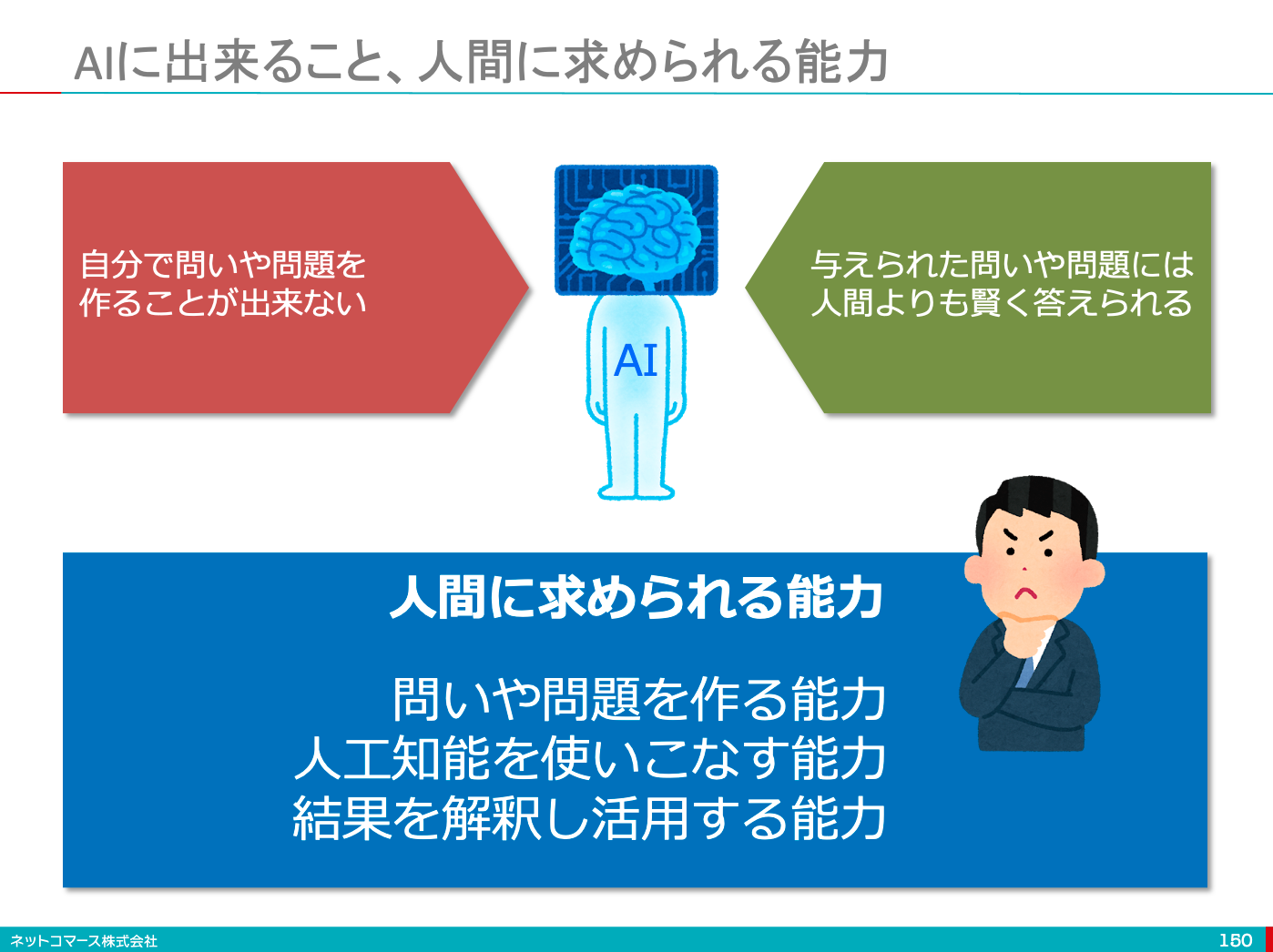
総務省の調査によると、有識者が重要視したのは以下の能力でした:
- チャレンジ精神・主体性・行動力・洞察力などの人間的資質
- 企画発想力や創造性
- 業務遂行能力や基礎的素養(これらは意外にも優先度が低い)
日本とアメリカの違い:働き方の文化が反映
同じ調査で、日本とアメリカの就労者の意識に大きな違いがありました:
アメリカ:「専門スキル重視」(51.9%)
- 情報収集能力
- 課題解決能力
- 論理的思考
日本:「人間関係重視」(35.9%)
- コミュニケーション能力
- コーチング能力
- チームワーク
この違いは、アメリカでは「自分のスキルに合った仕事をする」文化があるのに対し、日本では「スキルに関係なく、様々な仕事に対応する」文化があることを反映しています。
2024年現在:何が変わったのか

経済産業省が2024年に発表した「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方」では、新たな能力が求められています:
- ビジネスアーキテクト:選択肢から適切なものを判断する力
- デザイナー:独自視点の問題解決能力
- AI活用スキル:生成AIを使いこなす能力
- データリテラシー:データを正しく理解・活用する能力
楽しく体験!無料でできるAIフィギュア作成方法
AIの可能性を体験する最も楽しい方法の一つが、自分だけのAIフィギュアを作ることです。SNSでも大きな話題になっています。
Xで話題!実際のAIフィギュア投稿例
「AIフィギュア制作 楽しい♪
① Chat GPTでプロンプト生成
② Midjourneyで画像生成
③ TRIPO AIで3D立体モデル化
④ BambuLabで多色3Dプリント」– MITSUKI (@mitsuki_fab) X投稿より
「AIでフィギュア化に #AIイラスト #AI美女 #AIフィギュア」
– MAKIGAMI (@MAKIGAMI_red246) X投稿より
無料でできる!AIフィギュア作成の3つの方法
方法1:Fotorを使った基本的な作成
- Fotorにアクセス:https://www.fotor.com/jp/ai-image-generator/action-figure-creator/
- 写真をアップロード:フィギュア化したい人物の写真を選択
- スタイルを選択:アニメ風、リアル風など好みのスタイルを選ぶ
- 生成開始:数分待つと、フィギュア風の画像が完成
方法2:Pollo AIを使った高品質作成
- アカウント作成:Pollo AIに登録(無料で50クレジット付与)
- 画像をアップロード:元となる写真を選択
- プロンプト入力:「3D figure style, high quality, detailed」など
- 生成・ダウンロード:完成したフィギュア画像を保存
方法3:ChatGPTを使った創作フィギュア
- ChatGPTにアクセス:無料版でも画像生成可能
- プロンプト作成:「可愛いオリジナルキャラクターのフィギュア風イラスト」
- 詳細指定:髪の色、服装、ポーズなど細かく指定
- 修正・完成:気に入らない部分があれば修正を依頼
SNSで共有して楽しさ倍増!
作成したAIフィギュアは、以下のハッシュタグで投稿すると、同じ趣味の人とつながることができます:
- #AIフィギュア
- #生成AI
- #AIアート
- #AIイラスト
AI時代を恐れずに楽しく歩む5つの心構え
「AIに仕事を奪われる」という不安を抱く人は多いですが、実際にはAI時代こそ、私たちにとって新しいチャンスの時代です。
1. AIは「敵」ではなく「相棒」として考える
AIは人間の能力を拡張してくれるツールです。計算機が登場しても数学者がいなくならなかったように、AIが登場しても人間の価値は変わりません。
2. 「完璧」よりも「チャレンジ」を大切にする
平成28年の総務省調査でも明らかになったように、AI時代に最も重要なのは「チャレンジ精神」です。失敗を恐れずに新しいことに挑戦する姿勢が何より大切です。
3. 「人間らしさ」を大切にする
AIが得意なのは計算や分析ですが、以下のような「人間らしさ」はAIには真似できません:
- 共感力
- 創造性
- 倫理的判断
- 感情のこもったコミュニケーション
4. 学び続ける習慣を身につける
LinkedInの調査によると、「2030年までに必要とされるスキルの70%がAIによって変化する」とされています。だからこそ、常に新しいことを学ぶ姿勢が重要です。
5. AIを活用して自分の可能性を広げる
AIフィギュア作成のように、AIを使って今まで難しかったことが簡単にできるようになりました。これを機会に、新しい趣味や表現方法を見つけてみましょう。
現在のAI時代に求められる3つの新しい能力
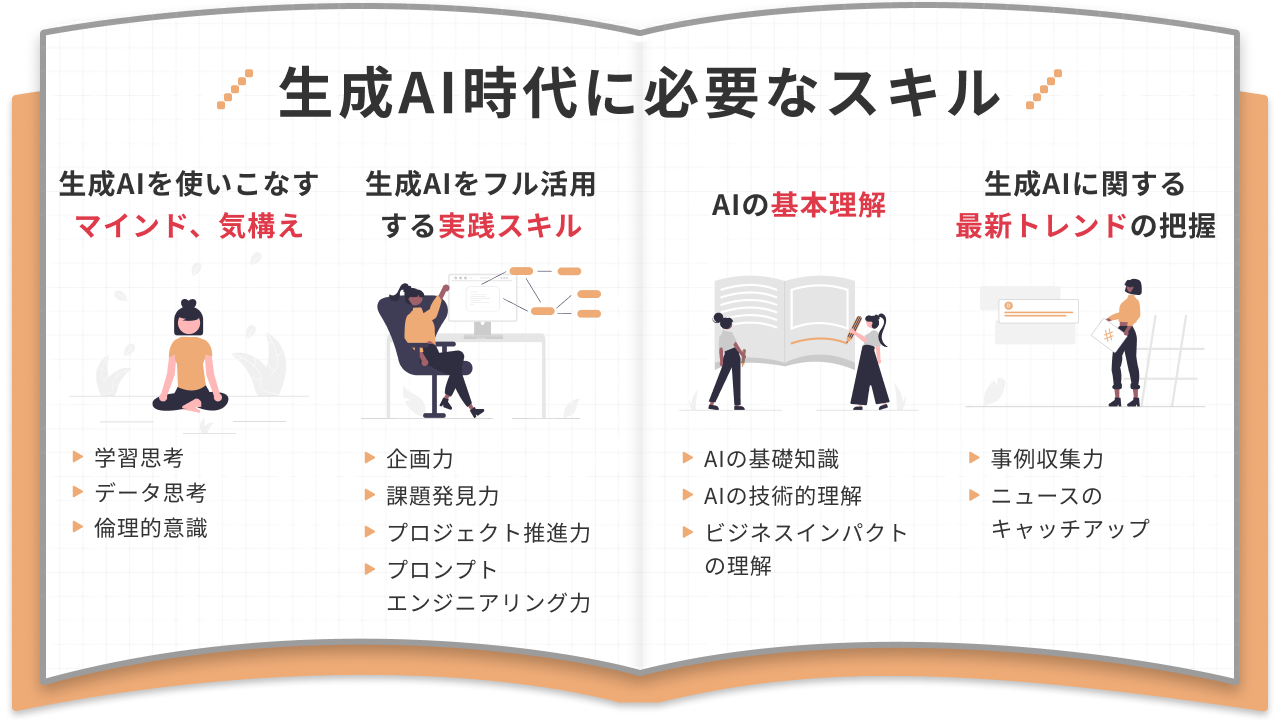
1. AI活用リテラシー
AIツールを適切に使いこなす能力です。具体的には:
- 適切なプロンプト(指示)を作成する能力
- AI生成結果の良し悪しを判断する能力
- 複数のAIツールを組み合わせて使う能力
2. 創造的問題解決能力
AIができない「0から1を生み出す」発想力:
- 新しいアイデアを考える力
- 異なる分野の知識を組み合わせる力
- 独自の視点で問題を捉える力
3. 倫理的判断力
AIが生成した内容の適切性を判断する能力:
- フェイク情報を見抜く力
- 著作権に配慮する意識
- 偏見のない公正な判断力
AIを使った新しい職業と可能性
AI時代の到来により、従来の仕事がなくなる代わりに、新しい職業も次々と生まれています。
新しく生まれている職業
- プロンプトエンジニア:AIに的確な指示を出す専門家
- AI倫理コンサルタント:AIの適切な利用方法を指導
- AIアートディレクター:AI生成コンテンツの品質管理
- 人間-AI協働デザイナー:人間とAIの協働をデザイン
既存の職業の進化
- 教師:AIを活用した個別指導の専門家に
- 医師:AIによる診断支援を活用する医療従事者に
- アーティスト:AIを創作ツールとして使う表現者に
具体的な学習方法:今日から始められること
初心者向け(中学生でもできる)
- ChatGPTを使ってみる:質問を投げかけて会話を楽しむ
- 画像生成AIで遊ぶ:好きなキャラクターを描かせてみる
- AIニュースを読む:最新のAI情報をチェックする
中級者向け(高校生以上)
- プログラミング基礎を学ぶ:PythonやJavaScriptの基本
- データ分析を体験する:Excel、Google Sheetsでデータを扱う
- AI倫理について学ぶ:責任あるAI利用について考える
上級者向け(大学生・社会人)
- 機械学習の基礎を学ぶ:オンラインコースで体系的に学習
- 自分の専門分野でAI活用を考える:業務への応用を検討
- AIコミュニティに参加する:勉強会やセミナーに参加
AI時代の不安を解消する3つの考え方
1. 「代替」ではなく「拡張」として捉える
AIは人間を置き換えるのではなく、人間の能力を拡張してくれるツールです。例えば:
- 計算が苦手な人でも、AIの助けで複雑な分析ができる
- 絵が描けない人でも、AIで美しいイラストを作れる
- 外国語が話せない人でも、AIで翻訳・通訳ができる
2. 「完璧」を求めすぎない
AIも完璧ではありません。間違いもあれば、偏見もあります。だからこそ、人間の判断力が必要なのです。
3. 「今」を大切にする
未来の不安ばかり考えるのではなく、今できることに集中しましょう。AIを使って楽しい体験をすることで、自然と慣れ親しんでいけます。
まとめ:AI時代を楽しく歩むために
AI時代は、私たちにとって新しい可能性に満ちた時代です。大切なのは、AIを恐れるのではなく、楽しみながら付き合っていくことです。
AI時代を楽しく歩む5つのポイント
- 好奇心を持つ:新しいAIツールを積極的に試してみる
- 学び続ける:常に新しい知識を吸収する姿勢を持つ
- 人間らしさを大切にする:AIにできない価値を磨く
- 創造的に考える:既存の枠にとらわれない発想を持つ
- 楽しむことを忘れない:AIを使って遊び、学び、成長する
AIフィギュア作成のような楽しい体験から始めて、徐々にAI時代の波に乗っていけば、きっと素晴らしい未来が待っています。今日から、AI時代を楽しく歩んでみませんか?
参考文献・出典
- 総務省「ICTの進化が雇用と働き方に及ぼす影響に関する調査研究」(平成28年)
- 経済産業省「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方2024」
- ブレインパッド「生成AIとは?AI、ChatGPTとの違いや仕組み・種類・ビジネス活用」
- NDIソリューションズ「ChatGPTと生成AIの全体像や違いを図解で丁寧に解説」
- X(旧Twitter)投稿:@mitsuki_fab, @MAKIGAMI_red246, @nbykos
※この記事は2024年7月時点の情報に基づいて作成されています。AI技術は日々進歩しているため、最新情報は各公式サイトでご確認ください。
 AI EBISU
AI EBISU 


