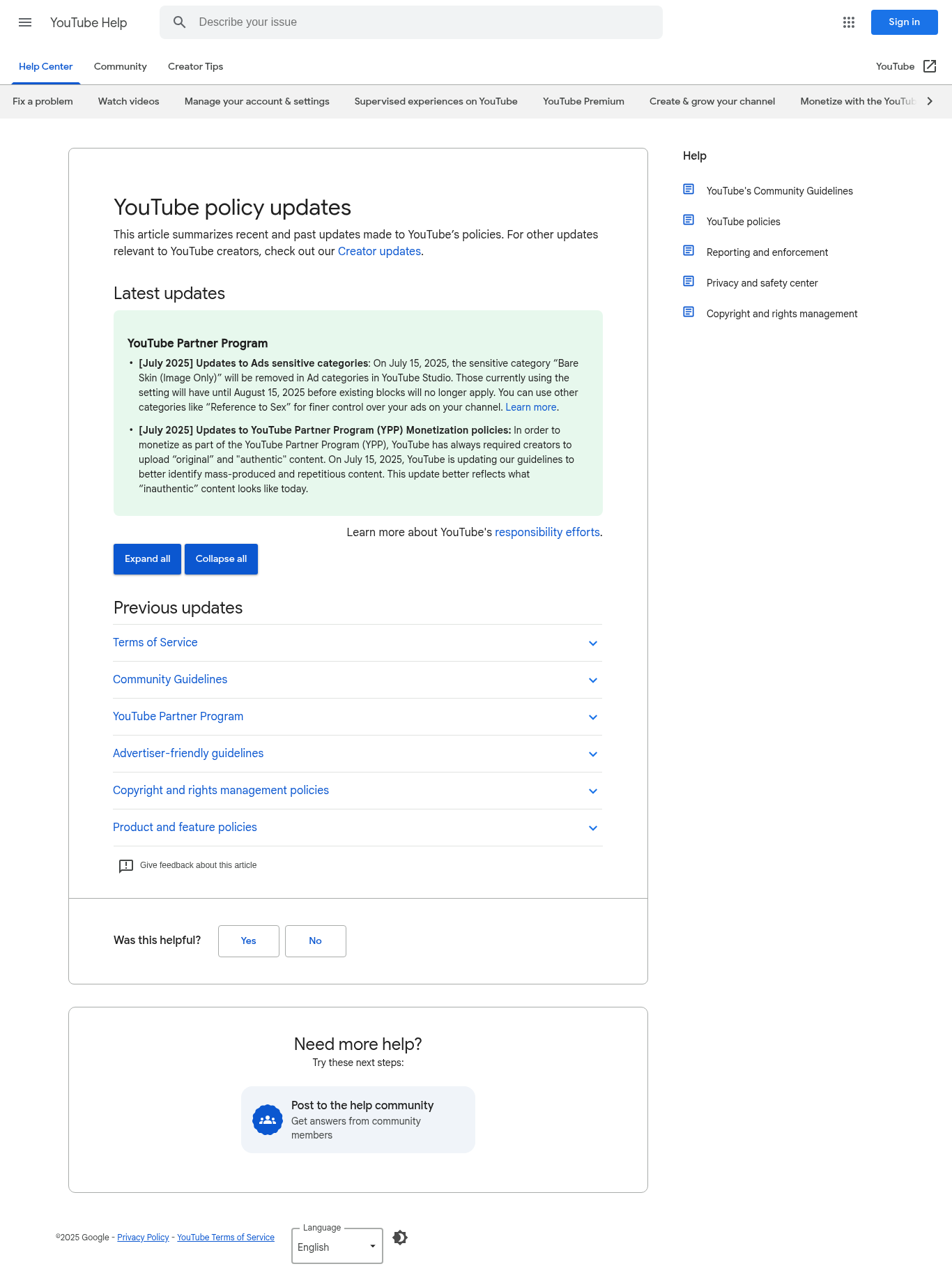2025年7月15日YouTube収益化ポリシー更新の全貌
YouTubeパートナープログラム改定の背景
YouTubeは2025年7月15日から、YouTubeパートナープログラム(YPP)の収益化ポリシーを更新することを発表しました。YouTube公式の変更ログによると、この更新は「大量生産された繰り返しの多いコンテンツをより適切に識別するため」のものです。
重要な点として、この更新は既存のポリシーを明確化するものであり、従来から適用されていたルールの執行を強化するものとなり、新しいルールが追加されるわけではありません。
Youtube公式発表の原文
出典:YouTube公式サポートページ – ポリシー更新情報
英語版原文
[July 2025] Updates to YouTube Partner Program (YPP) Monetization policies: In order to monetize as part of the YouTube Partner Program (YPP), YouTube has always required creators to upload “original” and “authentic” content. On July 15, 2025, YouTube is updating our guidelines to better identify mass-produced and repetitious content. This update better reflects what “inauthentic” content looks like today.
日本語訳
[2025年7月] YouTubeパートナープログラム(YPP)収益化ポリシーの更新: YouTubeパートナープログラム(YPP)で収益を得るには、クリエイターの皆様に「オリジナル」かつ「本物」のコンテンツをアップロードしていただくことが常に求められてきました。2025年7月15日、YouTubeは大量生産されたコンテンツや繰り返しの多いコンテンツをより適切に識別できるよう、ガイドラインを更新します。この更新により、今日の「本物ではない」コンテンツの実態がより明確になります。
公式発表の内容と海外の反応

出典:YouTube – René Ritchie氏による公式説明動画
海外では、この変更について様々な憶測や誤解が生じたため、YouTubeクリエイター・リエイゾンのRené Ritchie氏が動画で説明を行いました。
René Ritchie氏の説明
日本語訳
「7月2025年のYouTubeパートナープログラム収益化ポリシーのアップデートに関する投稿を見て、リアクションやクリップ、その他のタイプのチャンネルに影響すると心配している場合。私はRené Ritchieです。YouTubeで働くクリエイターです。事実はこうです。これは、コンテンツが大量生産されたり反復的であったりする場合をより適切に識別するための、YouTubeの長年にわたるYPPポリシーのマイナーアップデートです。この種のコンテンツは何年も前から収益化の対象外であり、視聴者がしばしばスパムと見なすコンテンツです。」
「マイナーアップデート」の真意とは
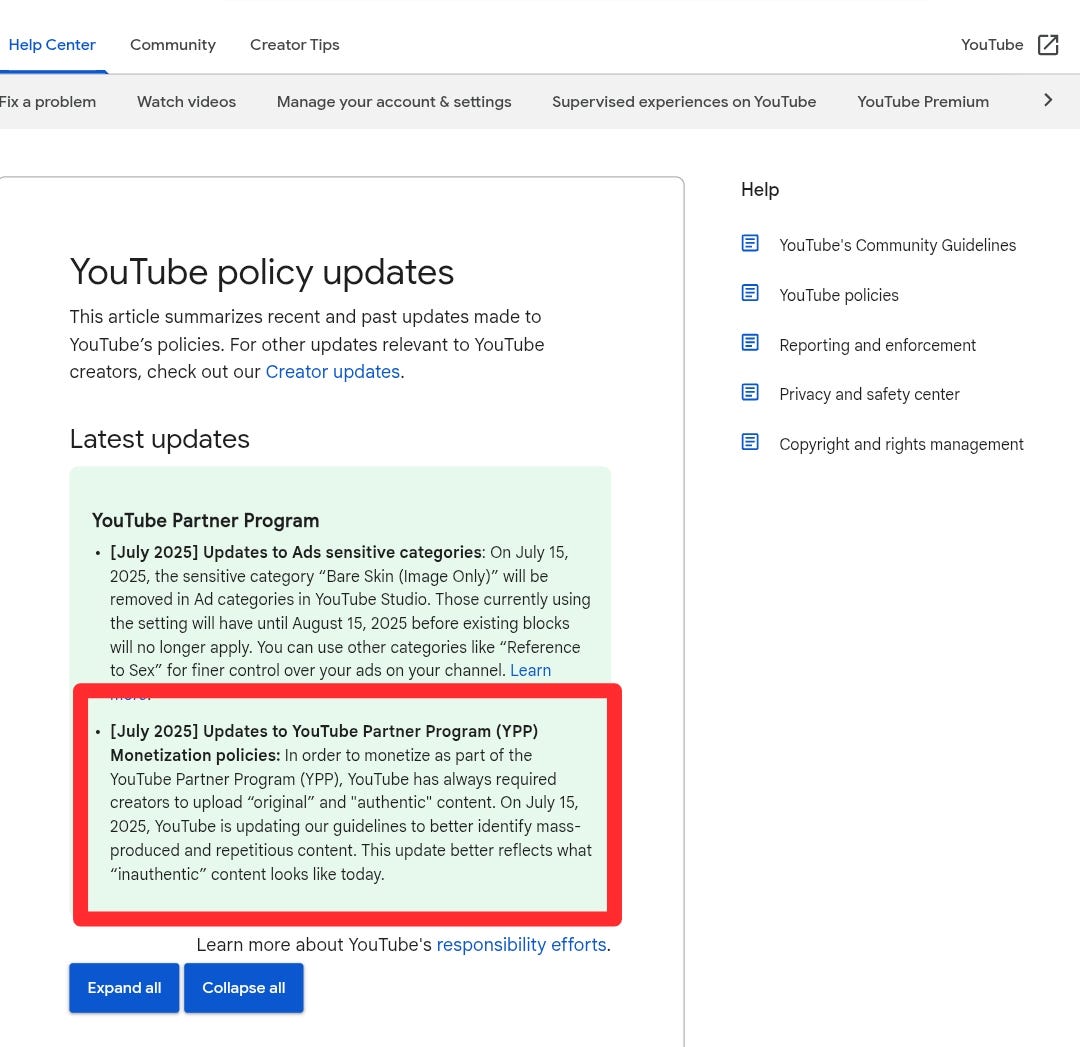
出典:Generative AI – YouTube 2025年7月15日アップデートの影響
YouTubeクリエイター・リエイゾンのRené Ritchie氏の説明によると、この変更は以下の特徴を持ちます。
- 既存ポリシーの明確化:新しいルールの追加ではない
- 執行強化:大量生産・反復的コンテンツの識別精度向上
- スパム対策:視聴者がスパムと見なすコンテンツの排除
つまり、この更新は既存のポリシーの執行を改善するものであり、根本的な変更ではありません。
収益化制限の対象となる「問題コンテンツ」を徹底解説
繰り返しの多いコンテンツの具体例
YouTube公式ガイドラインでは、「繰り返しの多いコンテンツとは、コンテンツが類似していて、視聴者がチャンネル内の動画の違いを識別するのが難しい場合を指します。これには、テンプレートを使用して作成されたと思われる、動画間であまり違いがないコンテンツや、簡単に大量複製されるコンテンツが含まれます。」と定義されています。

YouTube公式が挙げる収益化が許可されない具体例
このガイドラインに違反するコンテンツ(YouTube公式)
収益化が許可されない例(これらに限定されません)
- ウェブサイトやニュース フィードのテキストなど、自分で作成していない他の資料の内容を読み上げただけのコンテンツ
- 音程や速さを変えているが、それ以外はオリジナルと同じである曲
- 教育的な価値が低く解説や説明が少ない、繰り返しの多いコンテンツ、または漫然として意味のないコンテンツ
- 大量生産されたコンテンツ、または多数の動画で同じテンプレートが使用されているコンテンツ
- 説明、解説、教育的価値が最小限または皆無の画像スライドショーやスクロール テキスト
再利用されたコンテンツの判定基準
YouTube公式の定義
再利用されたコンテンツとは、すでに YouTube や他のオンライン ソースに存在するコンテンツを再利用し、独自の解説、実質的な変更、教育やエンターテイメント上の価値が十分に付加されていないチャンネルを指します。
YouTube審査担当者が調査する要素
コンテンツが再利用されていないかどうかを判断するため、YouTube の審査担当者はチャンネルを確認し、クリエイターがコンテンツをどのように発案、関与し、制作したかを調査します。審査担当者が調べるのは、チャンネルの以下の部分です。
- 動画
- チャンネルの説明
- 動画のタイトル
- 動画の説明
量産型・テンプレート動画の特徴
以下の表は、YouTube公式ガイドラインに基づく収益化可否の判断基準をまとめたものです。
| コンテンツタイプ | 収益化可否 | YouTube公式の説明 |
|---|---|---|
| 動画のイントロとエンディングは同じだが、コンテンツの大部分は異なる | 可能 | 「動画の中身が相応に異なるものであることが重要」 |
| 類似のコンテンツでも、各動画でそれぞれのテーマについて具体的に踏み込んでいる | 可能 | 「それぞれのテーマの性質について具体的に踏み込んでいる」 |
| 複数の短いクリップが編集でまとめられ、それぞれの関係性が説明されている | 可能 | 「類似する対象を扱った複数の短いクリップが編集でまとめられ、それぞれの関係性が説明されている」 |
| テンプレートを使用した動画間の違いがない大量生産コンテンツ | 不可 | 「大量生産されたコンテンツ、または多数の動画で同じテンプレートが使用されているコンテンツ」 |
| 画像スライドショーやスクロールテキストのみ | 不可 | 「説明、解説、教育的価値が最小限または皆無の画像スライドショーやスクロール テキスト」 |
AIコンテンツは本当に収益化NGなのか?
AI生成動画の収益化ルール
YoTube公式の「How YoTube Works? AI」ページでは、
AIに対する基本的な姿勢が明確に示されています。
「Our goal is to empower human creativity, not replace it. AI is the next creative revolution and we’re excited for how it will help viewers experience YouTube in new ways.」
(私たちの目標は人間の創造性を強化することであり、それを置き換えることではありません。AIは次の創造的革命であり、視聴者がYouTubeを新しい方法で体験できるようになることに期待しています。)
この公式声明から分かるように、YouTubeはAI技術そのものを否定しているわけではありません。重要なのは以下の観点です。
収益化が可能なAIコンテンツの条件
| AIの使用方法 | 収益化可否 | 具体例 | YouTube公式の指針 |
|---|---|---|---|
| 創造性を支援するツールとして | 可能 | Dream Screen、Auto Dubbing、AI Inspiration Tools | 「AI-powered tools are making content creation more seamless」 |
| 人間の編集・解説と組み合わせ | 可能 | AI音声に独自解説を追加、AI画像に創造的編集 | 「empower human creativity」 |
| 教育・解説目的での活用 | 可能 | 専門知識の解説にAI音声を使用 | 「providing helpful features」 |
| 完全自動生成・低付加価値 | 制限対象 | テンプレート化されたAI動画の大量生産 | 「mass-produced and repetitious content」 |
YouTubeが推奨するAI活用例
YouTube公式が提供・推奨するAIツールには以下があります。
- Auto Dubbing: クリエイターが動画を翻訳し、新しい視聴者にリーチできる
- Dream Screen: クリエイターがアイデアをShortsのAI生成背景に変換
- AI-Powered Inspiration Tools: 動画アイデア、タイトル、サムネイルの提案
これらのツールは全てYouTube公式が提供するものであり、適切に使用すれば収益化に何の問題もありません。
合成音声(ゆっくり・VOICEVOX)への影響
合成音声を使用した動画について、多くの誤解が広がっていますが、実際の状況は以下のとおりです。
YouTube公式のAI音声に関する見解
YouTube公式は、AIによる合成音声について特別な禁止事項を設けていません。重要なのは「開示要件」です。
「We require that creators disclose when realistic content is made with altered or synthetic media, including Gen AI Labels may then appear within the video description information, and if content is related to sensitive topics like health, news, elections, or finance, we may also display a label on the video itself.」
(現実的なコンテンツが変更されたメディアや合成メディア(Gen AIを含む)で作成された場合、クリエイターは開示する必要があります。ラベルは動画説明情報に表示され、健康、ニュース、選挙、金融などの敏感なトピックに関連するコンテンツの場合、動画自体にもラベルを表示することがあります。)
合成音声動画の成功事例
実際に、以下のような合成音声コンテンツが成功している例があります。
- 教育系チャンネル: 専門知識を分かりやすく解説するゆっくり動画
- 解説系チャンネル: 独自の調査に基づく分析動画
- エンターテイメント系: 創造的なストーリーテリング動画
これらのコンテンツに共通するのは、合成音声は手段であり、重要なのはコンテンツの質と独自性だということです。
問題となるAI素材の使用例
以下のようなAI素材の使用は、今回の制限対象となる可能性があります。
| 問題のあるAI使用 | 具体例 | なぜ問題なのか |
|---|---|---|
| 完全自動生成コンテンツ | AI音声 + AI画像のみの動画 | 人間の創造的関与が最小限 |
| テンプレート化された量産 | 同じ構成の睡眠・リラックス動画の大量投稿 | 「繰り返しの多いコンテンツ」に該当 |
| 低付加価値のコンピレーション | AI生成音楽のプレイリストのみ | 「説明、解説、教育的価値が最小限」 |
収益化可能なAI素材活用例
一方で、以下のようなAI素材の使用は問題ありません。
- 創造的な編集との組み合わせ: AI生成画像に独自のストーリーや解説を追加
- 教育コンテンツでの補助: 複雑な概念をAI画像で視覚化し、詳細に解説
- エンターテイメント要素として: AI音楽をBGMとして使用し、メインコンテンツは人間が制作
- アクセシビリティ向上: 多言語対応のためのAI音声使用
AIコンテンツ収益化の実践的ガイドライン
AIを活用しながら収益化を維持するための実践的な指針。
1. 開示の徹底
YouTube公式要件に従い、AI使用の適切な開示。
- 動画説明欄でのAI使用の明記
- 敏感なトピック(健康、ニュース等)では特に注意
- 視聴者への透明性の確保
2. 人間の創造性の前面化
AIは補助ツールとして使用し、人間の創造性を中心。
- 独自の視点や解説の追加
- 個人的な経験や専門知識の活用
- 視聴者とのインタラクションの重視
3. 質の重視
量より質を重視したコンテンツ制作。
- 各動画に明確な価値提案
- 視聴者のニーズに応える内容
- 継続的な改善と学習
4. コミュニティガイドライン遵守
AIを使用する場合でも、基本的なルールは同じ。
- 著作権の尊重
- 誤情報の回避
- コミュニティの安全性確保
結論として、AIコンテンツ自体が収益化NGというのは誤解です。重要なのは、AIをどのように使用し、どれだけの価値を視聴者に提供できるかということです。YouTube公式も「人間の創造性を強化する」AIの使用を積極的に支援しており、適切に活用すれば収益化に何の問題もありません。
切り抜き・リアクション動画への影響と対策
切り抜き動画が収益化停止になる条件
YouTube公式の収益化が許可されない例
収益化が許可されないその他の例(これらに限定されません)
- お気に入りの番組の一部を切り取った複数のクリップを編集でまとめただけで、説明がほとんどないか、まったくない
- 他のソーシャル メディアのウェブサイトのコンテンツを集めた短い動画
- さまざまなアーティストの曲のコレクション(許可を得ている場合も含む)
- 他のクリエイターによって何度もアップロードされたコンテンツ
- 他者のコンテンツのプロモーション(許可を得ている場合も含む)
- 別のオンライン ソースからダウンロードまたはコピーしただけで、実質的な変更が加えられていないコンテンツ
リアクション動画の生き残り方
René Ritchie氏の公式説明によると、今回の更新はリアクション動画を標的としたものではありません。
YouTube公式が収益化を許可するリアクション動画の条件
収益化が許可される例(これらに限定されません)
- 批評する目的でクリップを使用する
- 映画からシーンを引用して、会話を書き換えたり、ナレーションを変更したりする
- スポーツの試合のリプレイで、良い結果につながったプレーを解説する
- リアクション動画で、元の動画に対してコメントする
- 他のクリエイターの映像を編集し、ストーリーや解説を追加する
付加価値のある編集とは
YouTube公式が認める付加価値のある編集例
- アップロードしたクリエイターを動画の主役とするコンテンツ
- 他のオンライン ソースのコンテンツを再利用し、クリエイター本人が映っているか、どのような価値を付与したのかを解説するコンテンツ
- 動画の再利用コンテンツに音声や視覚効果を加えて編集された映像で、実質的な編集が行われており、チャンネル独自のコンテンツであることがはっきり示されている
YouTubeクリエイター審査の基準(公式情報)

YouTube公式の審査基準
YouTube の審査担当者が、チャンネルとコンテンツを YouTube のポリシーに照らして審査します。すべての動画を確認できるわけではないため、審査ではチャンネルの以下の要素が重視されることがあります。
- 主なテーマ
- 再生回数の多い動画
- 最新の動画
- 総再生時間の最も多くを占める部分
- 動画のメタデータ(タイトル、サムネイル、説明など)
- チャンネルの [概要] セクション
収益化停止を回避する具体的対策
オリジナリティを高める編集手法
YouTube公式の要求
YouTube で収益を得るには、コンテンツがオリジナルかつ本物である必要があります。コンテンツには以下のことが求められます。
- オリジナルの著作物であること。他者のコンテンツを借用する場合は、大幅に変更して独自性をもたせる必要があります。
- 重複コンテンツや繰り返しの多いコンテンツでないこと。コンテンツは、視聴回数を増やすことだけではなく、視聴者が楽しめる、または視聴者のためになることを目的として作成されている必要があります。
| 手法 | 説明 | YouTube公式の指針 |
|---|---|---|
| 独自の解説・コメント追加 | 専門知識に基づく分析 | 「視聴者が楽しめる、または視聴者のためになること」 |
| 複数素材の関連性説明 | 編集による文脈提供 | 「大幅に変更して独自性をもたせる」 |
| 実体験に基づく考察 | 個人の経験を活用 | 「オリジナルの著作物であること」 |
| 詳細な調査・検証 | 事実確認と分析 | 「本物のコンテンツ」 |
独自コンテンツの作成方法
YouTube公式の収益化ポリシーの目的
このポリシーの目的は、収益化対象のコンテンツを視聴者にとって関心や興味のあるものにすることです。つまり、一般視聴者から見て、チャンネルのコンテンツが動画ごとに違うとはっきりわかれば、収益化の要件を一つクリアしたことになります。
既存動画の見直しポイント
YouTube公式の警告
このポリシーはチャンネル全体に適用されます。つまり、YouTube のガイドラインに違反する動画が数多くある場合、チャンネル全体で収益化が無効になる可能性があります。
各ジャンル別の影響度と対策
ゆっくり解説・ボイロ解説チャンネル

出典:YouTube – ゆっくり霊夢・魔理沙とは?【解説動画】
影響度: ★★☆☆☆(中程度)
理由: 合成音声自体は問題ではなく、コンテンツの質が重要
対策:
- 独自の調査と分析に基づく解説
- 情報源の多様化と検証
- 視聴者とのインタラクション増加
まとめ系・雑学系チャンネル

出典:YouTube – 【雑学】9割が知らない科学のトリビア3選【ゆっくり解説】
影響度: ★★★☆☆(中程度)
理由: 他者の情報を単純に再編集するだけでは制限対象となる可能性
生き残り戦略:
- 独自の調査や検証の追加
- 専門家へのインタビュー実施
- 視聴者からの質問への回答
切り抜き・コンピレーション系チャンネル

出典:動画編集の教科書 – バズる!切り抜き動画のサムネイルを作る方法
影響度: ★★★☆☆(中程度)
理由: 単純な切り抜きでは付加価値不十分だが、リアクション動画は直接的な標的ではない
対策:
- 切り抜きに独自の解説追加
- 元コンテンツの背景情報提供
- 複数クリップの新たな物語構築
Xでのユーザーの声まとめ
YouTube収益化ポリシー変更について、Xでは様々な意見が交わされています。
まとめ
今回のYouTube収益化ポリシー更新は、クリエイターは過度に心配する必要はありませんが、自身のコンテンツが視聴者にとって真の価値を提供しているかを改めて見直す良い機会として捉えることが重要です。
- これは新しいルールではなく、既存ポリシーの執行強化
- AIコンテンツや合成音声の全面禁止ではない
- リアクション動画や切り抜き動画を直接標的としたものではない
- 問題となるのは「大量生産された繰り返しの多いコンテンツ」
- 独自の価値を付加したコンテンツは引き続き収益化可能
参考・引用リンク
YouTube公式情報
- YouTube のチャンネル収益化ポリシー
- YouTube パートナー プログラムの更新ログ
- YouTube の収益化ポリシー
- YouTube コミュニティ ガイドライン
- How YouTube Works – AI
YouTube公式動画
ニュース・報道
- Search Engine Journal:YouTube Clarifies Monetization Update
- TechCrunch:YouTube prepares crackdown on ‘mass-produced’ and ‘repetitive’ videos
- Times of India:YouTube’s new monetization rules
- Podcastle:YouTube Targets Unoriginal Content in Latest Policy Update
X(旧Twitter)でのユーザーの声
- 熊澤秀道 | ホリエモンAI学校CTO (@noumi0k)
- くりした善行 無所属 (@zkurishi)
- satoru (@satoru_inf)
- Yosuke Nagatomo (@gtmhouse)
 AI EBISU
AI EBISU